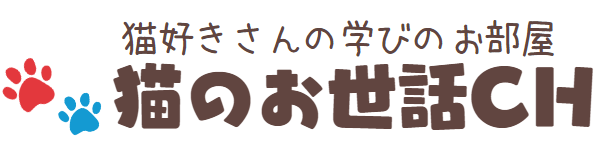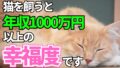皆さんこんにちは!
元・猫カフェオーナーによる猫のお世話チャンネルです。
このブログでは、猫を飼ってみたい方や飼い始めたばかりの方に向けて、
猫カフェが実際に行っているお世話の方法や使っているものをご紹介するブログです。
みなさんは猫ちゃんがなぜトイレを失敗してしまうかちゃんと理解していますか?
粗相をしてしまうのは、何らかの理由があると考えられます。
今回は粗相の原因と対策をまとめましたので、ぜひ参考までにご覧ください♪
トイレの環境
猫ちゃんがトイレを避けているような様子を見たことはありませんか?
猫ちゃんは綺麗好きで繊細な動物です。
粗相をしてしまうのはトイレの環境に不満があるのかもしれません。
トイレの大きさや形
まず、トイレの大きさや形が猫ちゃんに合っていない場合、猫ちゃんは不快感を感じてしまいます。
トイレが体に対して小さすぎると窮屈さを嫌って使わなくなってしまう可能性があります。
トイレの大きさは体長の1.5倍以上で方向転換できるほどの広さがあり、快適に使えるトイレを選ぶようにしましょう。
また、カバー付きやドーム型などトイレの形状が変わることでも不安を感じることがあります。
以前と違うタイプに変更した後に粗相が増えた場合は、トイレの形状が原因かもしれません。
特に高齢猫や子猫の場合は縁が高すぎるトイレや上から潜り込むようなタイプのトイレは負担がかかってしまいます。
そのため、段差の低いトイレを選ぶことが粗相予防につながります。
トイレの数を増やすことも粗相対策として有効です。
一般的にはトイレの数は飼育数+1個が理想的だと言われています。
猫ちゃんの数に合わせてトイレを適切に配置することで、排泄トラブルのリスクを大幅に減らすことができます。
以前、紹介させていただいた「ユニチャーム デオトイレ快適ワイド」は我が家の7kg超えの猫ちゃんでも問題なく使えています◎
トイレのサイズがかなり大きめで場所を取ってしまいますが、おススメの猫トイレです!
トイレの設置場所
次にトイレの設置場所も重要なポイントです。
猫ちゃんは静かで落ち着ける場所での排泄を好みます。
玄関近くやリビングの人通りが多い場所に設置されていると、安心して用を足せないため、トイレを避けてしまうことがあります。
安心して排泄できるよう、できるだけ静かで人の出入りが少ない場所にトイレを設置しましょう。
また、トイレの場所を変える際には、環境の変化に敏感な猫ちゃんに配慮し、一気に動かさずに少しずつ動かしていきましょう。
猫砂の種類
猫ちゃんは足裏の感覚が敏感で、砂の素材や粒の大きさが変わるとそれを嫌がって粗相をするようになることがあります。
新しい砂に変えてから粗相が始まった場合は、その砂の感触や匂いが合わなかった可能性が高いです。
猫ちゃんの好みや様子を見ながら最適な猫砂を探っていくことが大切です。
トイレの清潔さ
トイレの清潔さも非常に大切です。
猫ちゃんは本来、排泄物を埋める習性を持っているため、トイレが汚れていると掘るスペースがないと感じて他の場所をトイレにしてしまうことがあります。
ストレス
猫ちゃんは環境の変化に非常に敏感です。
引っ越しをした際などには見慣れた家具や匂い、音の全てが一変します。
これは猫ちゃんにとって自分の縄張りを失ったような感覚になり、安心できないまま過ごすことになります。
その不安が蓄積されると、トイレの場所が分かっていても使わなくなったりしてしまいます。
また、家具の模様替えなど部屋の雰囲気が変わっただけでも、いつもと違うと感じて落ち着かなくなることがあります。
さらに、家族に新しい人間の赤ちゃんや猫ちゃんを迎えた場合もストレスの要因になります。
縄張り意識が強いため、人間の赤ちゃんですら存在を脅威に感じられることも多いです。
自分の安心できる空間が奪われたと感じるとそれに対抗するようにマーキングや粗相をすることがあります。
一緒に居る時間を増やす
環境に変化があった時には強い不安や緊張を感じてしまうことがあります。
そのようなときは安心できるように、一緒に過ごす時間を意識的に増やすことが大切です。
例えば、好きなおもちゃで遊んであげたり、静かにそばに座っているだけでも猫ちゃんにとっては大きな安心感になります。
猫ちゃんは自分のペースを大切にする動物なので、べったりと接する必要はありません。
パーソナルスペースの確保
猫ちゃんが安心できる”自分だけの場所”を確保することも重要です。
高い場所や囲まれた空間は猫ちゃんに安心感を与えます。
キャットタワーや段ボール箱などを取り入れてみましょう♪
発情
発情期になると自分の縄張りを他の猫ちゃんにアピールするため、通常のトイレとは別の場所でおしっこをする”スプレー行為”を行うことがあります。
このスプレー行為とは、ただ単に排泄をしているのではなく、少量のおしっこを壁や家具などに向かって噴射するように排出する行動を指します。
強い匂いのあるおしっこをマーキングとして使うことで”ここは自分のテリトリーだ”と主張しているのです。
このスプレー行為は、一般的にオスに多く見られるものですが、発情したメスでも行うことがあります。
家具や壁にされた場合は匂いが染みつきやすく、掃除も大変になります。
去勢・避妊手術をする
去勢・避妊を行うことで性ホルモンの分泌が抑えられ、発情による衝動的な行動が軽減されます。
できるだけ早い段階で去勢・避妊の手術を検討することが重要です。
発情行動が目立ち始める前に手術を済ませておくことで、粗相の予防にもなり、飼い主にとっても猫ちゃんにとっても快適な生活環境を維持しやすくなります。
また、猫用フェロモン製品である「フェリウェイ」を使用してみるのも効果的です。
フェリウェイ
フェリウェイを散布することでフェロモンが満たされ、これ以上マーキングする必要をなくし、問題行動を抑えてくれます。
老化
猫ちゃんが年を取るにつれて、動く時間が減ってきたなと感じる方も多いのではないでしょうか?
シニア猫になると、私たち人間と同じように体のあちこちに不調が現れ始めます。
特に、足腰の筋力が弱まることや関節の柔軟性が失われることは、日常のあらゆる動作に影響を及ぼします。
これまでなんなく使えていたトイレの縁をまたぐことが負担になってしまうことがあります。
特に高さがあるトイレの場合や、段差がある場所にトイレが設置されていると、トイレまでの移動や出入りが億劫になり、間に合わずにトイレの外で排泄してしまうことが起きやすくなります。
さらに、関節炎や腰痛といった慢性的な痛みを抱えているシニア猫は、排泄の際に腰をしっかりと落とすことが難しくなります。
そのため、排泄物の位置がずれてしまいトイレの中でしているつもりでも、結果的にトイレの外にこぼれてしまうケースが見られます。
病気
粗相をするのは何か病気をしているサインかもしれません。
猫ちゃんは膀胱炎や尿路結石、腎不全といった泌尿器系のトラブルを起こしやすいです。
これらの病気にかかると、排尿コントロールが難しくなり、間に合わずに粗相をしてしまうケースが多く見られます。
膀胱炎にかかると排尿時に痛みを伴うことがあり、その痛みを恐れてトイレを避けるようになることがあります。
尿路結石の場合は、尿道が詰まりやすくなり尿はあるのにうまく排出できず、不快感や苦痛から異常な場所での排泄行動につながることもあります。
慢性腎臓病を抱えるシニア猫では尿の量が増える多尿という症状がよく見られます。
体内の水分がうまく再吸収されずに大量の尿として排出されるため、排尿回数も自然と増えていきます。
そうなると以前よりもトイレに行く頻度が高くなり、少しのタイミングのずれで間に合わなくなってしまうことがあるのです。
我が家でも10歳を超える猫ちゃんがお尻を浮かせておしっこをしている時期があり、トイレの外にまでおしっこがはみ出していました。
病院に行って調べてもらうと、膀胱結石ができてしまっていました。
手術で石を除去してもらうとそのような粗相はなくなり、現在ではちゃんとトイレ内で排泄できるようになっています。
病院へ受診をする
粗相が続いて何らかの異常が見られる場合、すぐに困った行動として扱うのではなく、早急に動物病院を受診することが大切です。
病気を早期発見するためには日々の観察が欠かせません。
水分摂取量や体重の急な増減はないか、排泄物の色や頻度の変化はないか、毛づくろいの頻度など普段との違いに気づくことで病気の早期発見につながります。
健康維持のためには年に1度は健康診断を受けるようにしましょう。
特に7歳以上のシニア猫は半年に1度の受診が理想的です。
粗相が続く場合は叱るのではなく、まずは健康状態をチェックしてみてくださいね♩
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、猫ちゃんの粗相の原因と対策でした。
猫ちゃんの気持ちを理解して、寄り添いながら対策をしていきましょう♬
最後までお読みいただきありがとうございました!